こんにちは。京都市中京区にある西山浄土宗・満福寺の住職。また六満こどもの家(夜間保育園)の園長をしています。しゅうじょうです。
私自身、ある方の言葉から前向きになれるような考え方になれた経験から、明日が大好きになれるような言葉を発信しています。
今日の「明日が大好きになれる言葉」は・・・
『ありのままを受け入れて生きる』です。
チャイルド・ライフ・スペシャリスト
この言葉は、闘病生活をしている子ども達と、話したり遊んだり一緒に過ごす中で子ども達の「見えづらい感情」をくみ取り、子どもたちの本当の思いを医師や看護師に伝える「子どもの代弁者」であるチャイルド・ライフ・スペシャリストという資格をもつ佐々木美和(ささきみわ)さんがTEDトークで話されたときの言葉になります。
佐々木さんが大切にしていること・・・
それは、「ありのままを受け入れて生きる」ということ。
佐々木さんは英語が大の苦手で、この資格を取得するために行った、北米での保育園の実習では子どもたちと英語でコミニュケーションを取ることがまったく出来ず、
「子どもの言っていることがまったく分からない」、「子どもに自分の思いが全然伝わらない」など毎日のように悩む日々が続き、大きな挫折を経験されたそうです。
しかし、その実習の指導教官の先生から
「あなたは確かに英語は話せない。私たちと同じように子どもと関わることはできない。でも、言葉が不自由な分、私たちには見えてないものが見えている。あなたにしかできない関わり方がある。だからそのままでいいのよ」という言葉をかけてもらったそうです。
この言葉のおかげで佐々木さんは気持ちがとても楽になったと言っておられます。
言葉の力って本当にすごいですね。辛い時でも一つの言葉で前を向くきっかけに繋がる。私も言葉の力で気持ちがとても楽になった経験から、今では自分の発する言葉を大切にするように心掛けています。
私の言葉がきっかけになり一人でも多くの方が笑顔になってもらえると嬉しいですね。
佐々木さんは、この言葉を聞いてからは、出来ない英語を上達させようともがくのをやめて、出来ない自分を受け入れて、「私、英語できないの教えて」とありのままの自分で子どもと向き合うようになれたそうです。
すると、不思議なもので子ども達の方も佐々木さんのことを受け入れてくれるようになり、辛かった実習もどんどん楽しくなっていき、子ども達とも深く関われるようになったそうです。
『他人と比べるのをやめて、ありのままの自分を受け入れる。そして、ありのままで相手と向き合うとお互いに少し心を開いて良い関係が築けるのかもしれない」と佐々木さんは言っておられます。
もう一つの大切にしていること
佐々木さんが仕事をする中で、もう一つ大切にしていることがあるそうです。
それは、アメリカで子どものホスピスでの研修時に上司から「サポーティブ・インパクト(~をしてあげる)」ではなく「サポーティブ・エンバイロメント(~に寄り添う姿勢)」であってください」と教えてもらえたことだそうです。
「サポーティブ・インパクト」
何か与えてあげるという一方通行の矢印。→「私がしてあげる」
「サポーティブ・エンバイロメント」
何かをするわけではなくて、ただその人のことを思ってそこにいる。→「相手に寄り添ってあげる」
ある男の子からの一言
佐々木さんが日本の病院で働きはじめたときに、ある男の子からこんな言葉を聞いたそうです。
その日は病棟でお楽しみ会のイベントをしていて、佐々木さんが彼の部屋に行って「一緒にお楽しみ会行く?」と声をかけると、
「今日はいい。やめとく。だって気を使うじゃん。笑ってあげないといけないでしょ」と言われたそうです。
その彼の言葉に、佐々木さんは「はっ」としたそうです。
子どもは大人の「楽しませたい」「笑ってほしい」という気持ちを空気を読んで、気を使って笑ってくれていることがあるんだなと思ったそうです。
でも、佐々木さんが目指すのは、子どもが気を使って笑ってくれる関係じゃない。嫌な時は「嫌」と言える。「あっち行け」と言える。泣きたいときは一緒に泣ける。そんな関係でいたいと、彼のその言葉を聞いたときに感じたそうです。
私たちは、誰かの力になりたいと思うとき、気をつけていないと「サポーティブ・インパクト」になってしまいがちになってしまいます。
つまり、「何かをしてあげる」「誰かを楽しませる」「笑わせる」というような「私が」笑ってほしい、「私が」役に立ちたいというような「私が」主語になってしまうことがある。
そのとき、その人は笑いたくないのかもしれない。泣きたいのかもしれない。ただ、のんびりお昼寝がしたいのかもしれない。
「私が」という自分の気持ちを少し引っ込めて、ありのままの相手を受け入れて、また違いを受け入れて、寄り添うという姿勢でいられたら、その時、その人が本当にしたいこと、本当の気持ちが見えるのかもしれない。
私達は、人生で誰かのためと思って何かをするとき、「してあげる」という気持ちを持ちがちですが、佐々木さんによると、そうではなく、ただその人を思って側にいる、寄り添うことがとても大切だということを話しておられました。
私も僧侶として、困っている人に対して、何かをしてあげないといけないと思うことも多かったと思います。
しかし、「してあげる」という気持ちが強くなりすぎると、「私が」役に立ちたいというような、「私が」主語になってしまっていたなと振り返ることができました。
話をしなくても、ただその人を思って側にいるだけ、寄り添うことたけでもその人の救いになるかもしれないということを知れて私自身とても気持ちが楽になりました。
私たちに100%の確率で起きることとは!?
人生や物事に「100%」は起こり得ないことが多いと思いますが、それでも誰もが100%の確率で起こることがある。
それは「死ぬ」ということ。
この「死ぬ」ということは当たり前のことですが、普段はあまり意識しないのかもしれません。
でも、私たちは間違いなく、みんな100%の確率で死にます。
この事実をどう受け止め、受け入れて考えていくか。佐々木さんはここに希望が見出せるのではないかと感じたそうです。
そして、具体的に、死を間近にしながらも、懸命に生きていた、そして、今を大切に生きている少年「たいじゅ君」と「よしき君」のことを最後にTEDトークの中で話をしてくれました。
たいじゅ君とよしき君の話
たいじゅ君の話
たいじゅ君は中学の時に病気が発症し、一旦は元気に退院したのですが高校生になるころ、病気が再発してもう治せないという状況になりました。
16歳のときに医師から「もう治せない」ということを伝えられたそうです。
そして、抗がん剤の治療は気持ち悪くて辛くて大嫌いだったので最後は自分で「もうこれ以上治療はしない」と選び決めて亡くなりました。
治療をやめて亡くなるまでの間、彼がとても穏やかに家族と思い出話をしたり、ガンダムのプラモデルを作ったり、会いたい人に会ったりして過ごしていたそうです。
たこ焼きパーティーでの出来事
佐々木さんはたいじゅ君との印象的なエピソードを話してくれました。
中高生が集まってたこ焼きパーティーが始まれば、カラシ、ハチミツ、チョコレートが入ります。
そんなたこ焼きをよく食べさせられていたリアクション抜群の看護師さんがいたそうです。みんなで楽しくおしゃべりをしていたとき、たいじゅ君がその看護師さんに聞きました。
「ねぇ たこ焼き 何が一番まずかった?」
その看護師さんは「グミだね ブドウのグミが最悪」と答えました。すると、たいじゅ君は佐々木さんにこう言ったそうです。
「佐々木さん 分かった?グミだって。今度のたこ焼きのときは忘れずにグミ用意しなきゃダメだよ」と
「今度のたこ焼きのとき・・」というのはもう自分がいない時、自分は参加できないたこ焼きパーティのことです。
彼は自分がもうすぐ死ぬという事実をもちろんいろんな気持ちがあったと思いますが、そんなユーモアを持って受け入れてたと思うと佐々木さんは話されていました。
最後にこんな手紙を残してくれたそうです。
「最後まで楽しく過ごすことができて幸せだった。今まで、ありがとう」
よしき君の話
次はよしき君の話をされました。たいじゅ君を見送ってからよしき君も病気の再発を告げられました。そして、彼もまた医師から「もう治せない」と告げられました。
それでも彼は最初、「治すために治療を続ける」といって病院で辛い抗がん剤治療を続けていました。
『たとえ機械に繋がれて動けなくなっても、治療を続けていればそれは頑張っていると言えるのだろうか、諦めて良いのか』
今まで「病気に負けるな。頑張って闘え」そう言われ、そう強いられてきた彼らです。そんな彼らは医師に「もう治せない」と言われてもなお治療をやめることは諦めること。
そう感じるのかもしれないと佐々木さんは感じたそうです。
そのとき、佐々木さんはよしき君に
『治療をしてもしなくてもいい。どんな選択をしてもそれはどう生きるか?という生き方の選択。諦めではないよ。どんな選択をしてもいいんだよ』と
あるがままの自分の姿を受け入れてもらった青少年の心の重荷は、佐々木さんの言葉によって、きっと軽くなったのだろうと思います。
そして、よしき君は後日、佐々木さんにこのように言ったそうです。
『治すことは諦めた、でも、生きることは諦めない。』
そして、よしき君は治すためではなく少しでも家族といい時間を過ごすことを目標に副作用の少ない薬に変えたり、薬の量を減らしたりという選択をしているそうです。
「生きることは諦めない」そう言うよしき君は「時間を大切に生きたい。そして、自分にできることをしたい」と周りの人に伝えているそうです。
そして、自分が生きている間に、何かできることを探し、みんなの為を思って愛知知事に、院内高校を設ける為のお願いの手紙を出したという行動力、そしてそのことがきっかけになり、高校の院内訪問教育が制度化されスタートすることに繋がりました。
この生きることを諦めないその姿勢に私も本当に心が動きました。
佐々木さんは自分の命の限りを受け入れて、今を大切に生きようとしているよしき君、もうすぐ死ぬという事実をもちろんいろんな気持ちがあったと思いますが、色々なユーモアを持って受け入れ、目の前の一瞬を大切に生きた、たいじゅ君。2人は本当に大きなものを残してくれたと言っておられました。
「命は誰でも必ず終わりがやってくる。大切なのはその時間の長さではない」と思っていると佐々木さんは言っておられます。
命の時間が長くても短くても自分に与えられた命の時間を受け入れて、その時間をどう生きるのか?それが大切なのだと。どんな選択、どんな生き方も価値あるものです。日常もたくさんの選択のくり返しです。
悩むのも当然、迷うのも当然ですが、どんな選択をしてもあとから振り返ったときに「良かった」「幸せだった」と自分で自分の選択や生き方を受け入れられたら素晴らしいと思う。
それは、たいじゅ君やよしき君をはじめ佐々木さんが関わった多くの人が教えてくれたことだと言っていた。
ニーバーの祈り
佐々木さんは、最後に「ニーバーの祈り」を紹介して下さいました。
「変える事が出来るものについては、それを変えるだけの勇気を
変えることが出来ないものについては、それを受け入れるだけの心の平静を
そして変える事が出来るものと変える事が出来ないものを見極めるだけの賢さを与えてください」
ニーバーの祈り
このニーバーの祈りは、1943年、ラインホルド・ニーバーがマサチューセッツ州西部の山村の小さな教会で説教した時の祈りが始まりとされています。
第二次世界大戦の中、この祈りの言葉が兵士たちに広まり、戦後にはアルコール依存症克服のための組織のモットーとして採用され、世界中で広く知られるようになりました。
私たちは自分の過去を変えることは出来ません。
どんなに恨んでも嘆いても、幸せな過去の記憶という風に急に変わることはないと思います。
「私に与えられた命の時間を受け入れて、不甲斐ない自分も受け入れて、今を大切に生きたいと思っている」と佐々木さんは話を終えられました。
変えられないのなら、ありのままを受け入れることで未来は必ず変えられるはずである、大切なのは諦めずに、出来ることから頑張る事が大切なのだと、佐々木さんの講演を拝聴し、感じました。
私たちは生まれたら、必ず死にます。つまり余命を生きています。その余命をどうのように生きますか?
誰もが幸せに生きたいと思っていると思います。
そして、それこそが本来の目的なのだと思います。あれがない自分は不幸だと思うのではなく。目の前のありのままを受け入れて生きる。その目の前の幸せをたさん感じて生きていけることが幸せになる秘訣なのだと私は思います。
今日が一番若い日です。今日は今日にしか来ません。今日一日を大切にして「ありがとう」にあふれた素敵な一日にできたらいいですね。
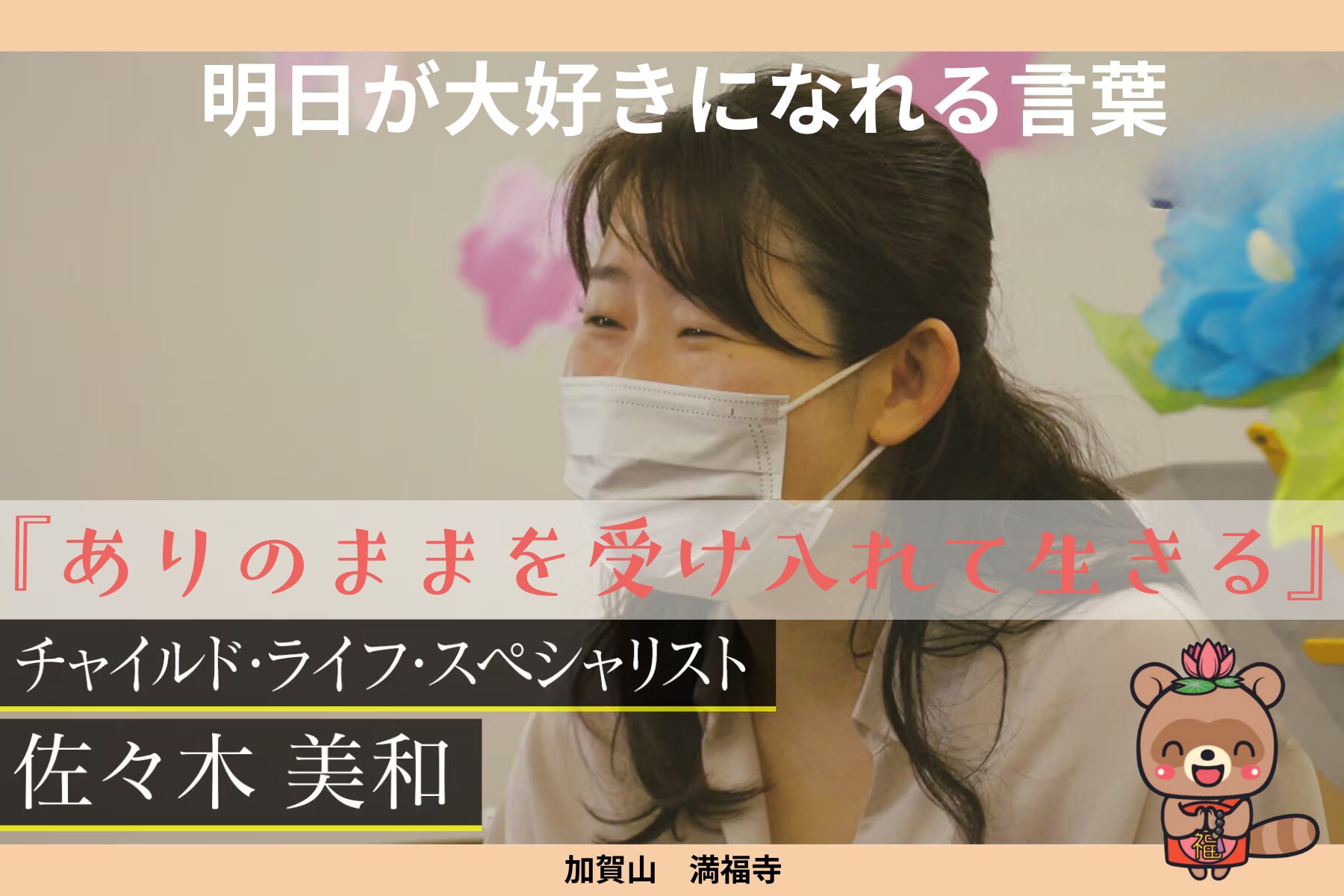

コメント